2023.09.19 TUE
未来の「よき先祖」になるために、いま私たちができること
大瀧裕樹 ✕ 中間真一
連載対談「自然社会を迎える瞬間」vol.3
SINIC理論をベースに、未来の展望やよりよい未来づくりについて
自由で活発な議論を交わす連載対談

これからの時代における「SINIC(サイニック)理論」の役割や未来への視座を再確認することを目的とした連載企画「自然社会を迎える瞬間」。
生物学者の福岡伸一さんとヒューマンルネッサンス研究所 エグゼクティブ・フェローの中間真一がナビゲーターとなり、多様な専門性を持つゲストをお招きします。
連載3回目となる今回は、日本たばこ産業株式会社で新しい事業の可能性を探索する“特殊部隊”D-LAB(Delightful Moment-Laboratory)を率いる大瀧裕樹さんと、SINIC理論をオープンソース化して社会に浸透させる取り組みを実践するヒューマンルネッサンス研究所 エグゼクティブ・フェローの中間が、よりよい未来を構築するために企業がすべきことについて語り合いました。
―― 新しさは、極論に走らない思慮深さから生まれる
中間:先日、広島でG7サミット(主要国首脳会議)が開催されていました。そこで議論されていたのは新型コロナウイルスによるパンデミックへの対応や気候変動が及ぼす将来的な影響、ウクライナ危機など、SINIC理論に即して言えば「最適化社会」から「自律社会」、そして「自然社会」へと向かっているグローバル社会のパラダイムシフトの課題だと感じます。
大瀧さんは日本たばこ産業株式会社(以下、JT)でD-LAB(※1)を率いていらっしゃいます。その取り組みは、昨今の大企業に目立つような短期的利益追求とは異なる指向性を感じます。その背景などをお聞かせいただけますか?
大瀧:ありがとうございます。質問にお答えする前に、本日訪れている「立石一真 創業記念館」で拝見したオムロン創業者・立石一真さんの言葉に深く感銘を受けました。特に「最もよく人を幸福にする人が、最もよく幸福になる」という言葉は、『ワールドハピネスレポート2023』(※2)で言及されている幸福論や利他性の重要さにも通じるものを感じました。
さて、質問にお答えします。JTは、制度・組織体としては1898年の専売局設置に始まり、1985年に会社化されました。現在は、私たちのJT Group Purposeとして「心の豊かさを、もっと。」を掲げ、世に届けるための方法を模索しています。D-LAB(D: Delightful Moment)はその活動のひとつであり、文字通り心の豊かさを提供するための取り組みを行っています。特徴的なことは、従来の大企業や日本企業、JTの手法とは異なるアプローチを追求していることです。
中間:逆の方向性とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
大瀧:いくつかの視点がありますが、例えば20世紀における連続的な経済成長を前提とした企業経営では、どちらかというとWHAT、HOW、WHYの順序でビジネスが成立していました。つまり産業・事業(WHAT)と戦い方・手段(HOW)がまず起点にあり、理由・目的(WHY)は軽視されてきた傾向があった。
しかし、私たちはこれの逆、WHY、HOW、WHATの順序で行動することを重視しています。それはまさに作家・思想家のサイモン・シネックが提唱するゴールデンサークルという概念ですが、D-LABという組織ではWHYを唯一の起点とし、そこに心の豊かさを位置づけています。そこから最終的に何ができるかは私たち次第です。
また、私たちは長期的な視点を持つことを大切にしていたり、「こっちがいい」「こっちが悪い」という二元論に終始しないということも同時に重要視しています。具体的には、持続的で長期的な事業の実現には、JTが捉えられている未来の論点仮説を演繹的に思考して視野を広げていく、内側から外側に向かって世の中を洞察するインサイド・アウトの思考が大切であると同時に、SINIC理論などの概念や発想に基づき、普段我々があまり把握・意識できていない情報を未来の変化の予兆として扱うアウトサイド・インの思考も取り入れています。このように異なる視点や思考方法をバランスさせる、これまでの我々には不足していた異なる視点も同時に尊重することを心掛けています。
中間:なるほど、興味深いアプローチですね。新しい視点を取り入れると同時に、異なる視点をリスペクトすることで、より多様性や包括性を持った取り組みが可能になるということですね。
※1 D-LAB:JT内に設立された部署。たばこ事業に縛られることのない、新しい事業の可能性を探索する“特殊部隊”のような位置づけの活動をしている。
※2 World Happiness Report 2023:国際的研究機関「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」(SDSN)が発表する“世界幸福度報告書”。
―― 線ではなく、円環から読み解く長期思考

中間:従来の日本企業や社会では、なかなか長期思考が難しいと感じられることがあります。というのも、短期的な数字に焦点を当てて評価をする傾向が強いからです。企業が長期的な視点に立つために必要なこととは何でしょうか?
大瀧:私がアメリカに留学していた2006年当時、戦略の観点で未来洞察や未来予測などを学ぶ中で、利益を適切に社会へと還元していく“円環性”の不足に気付く機会がありました。その後、SINIC理論との出会いがあったのですが、この理論こそが唯一無二の円環的なアプローチを持っていると感じました。
ともすると、短期志向を積み上げていくと長期志向があまり重要ではないと考えてしまいがちですが、社会における起業の役割を俯瞰していくと、長期志向も大切だということがわかります。もちろん短期的な利益も大事ですし、短期思考に長期的な思考をどう取り込むかも重要です。どちらがより大事かということではなく、両者のバランスを取ることが大切なのだと思います。
中間:大瀧さんとSINIC理論の出会いとヒットポイントは、とても嬉しい話です。今でこそ「両利きの経営(※3)」という言葉が出てきているわけですが、それに先駆けて、アメリカで気がつかれたわけですね。
大瀧:そうですね。私が留学していた2006年当時の米国は、論理性や合理性、標準化が評価基準であり、企業活動も短期的な成績や収益に焦点を置くことが主流でした。しかし、私はそれに対して本当にそれだけでよいのか、それ以外にも大切なことはあるのではないかと考えながら授業を受けていました。SINIC理論に興味を持ったのは、その円環的なアプローチに共鳴したからです。また、企業や社会において感情や情緒性などを取り入れることの重要性を考えるきっかけにもなりました。
中間:企業の社会化や人間化を目指すということですね。
大瀧:そうです。私たちは時折、社会の存在を忘れてしまっているように感じます。円環性を重視し、感情や情緒性などを社会や企業に組み込むことで、より豊かな環境を創り出せるのではないかと考えています。
中間:そうですね、円環や循環という概念はSINIC理論の大きな特徴のひとつだと思います。SINIC理論では、単に直線あるいは指数関数的な成長をするだけではなく、円環状に上昇していく成長プロセスを重視しています。これは企業が長期的な視点を持つ上で非常に重要です。

100万年前の原始社会から始まる人類の歴史を考えてみましょう。最初は道具も少なく、心が重視される社会だったはずです。農業革命以降、人類社会は急速に進展し、ルネサンスが起こり、近代科学が生まれ工業化が進んでいきました。その過程を経て、社会の持つ価値観も心を重視することから物・物質を重視するように変化していきます。
一般的な未来予測ならば加速度がついて、まっしぐらに成長が進むと考えるところですが、SINIC理論では螺旋階段を登るように、行き来を繰り返しつつ円環的に発展することで、最終的に「自然社会」という状態に至ると考えています。この「自然(しぜん)社会」は、より現代の実情に即した視点から未来を見れば「自然(じねん)社会」と呼んだ方がより適切だと言えるかもしれません。こうした考え方は仏教哲学など東洋の思想を取り入れています。人類の進歩を促してきた西洋の哲学とも結びつき、円環を形成しているという点も重要なポイントだと思います。
ですので、冒頭で触れたパラダイムシフトというのは、まさに人類史上最大の変革であり、心から物質へと移行した後に再び物質から心へと方向転換をしている時期だと考えています。その転換点に気づかずに進んでいく中で、イナーシャ(慣性力)が働いて、そのカーブを曲がりきれなくなる心配もありますが、気がつく感受性を持っている人々はSINIC理論が提案する円環的な回帰へと向かえるはずです。大瀧さんの話もまさにそこに目が向けられており、心という要素を前例のないプロセスで重視していると感じました。
※3 両利きの経営: 米スタンフォード大学経営大学院教授のチャールズ・オライリーが提唱する、企業活動における知の「探索」と「深化」の高度な両立を実現する経営のこと。
―― 未来の「やっておいてよかった」を今、つくろう

大瀧:SINIC理論は昨今のサスティナビリティに関する議論を補完する役割もあると思います。サスティナビリティの議論は、環境や資源の有限性が大事であることは論をまたないですが、世代間の公平性や継承性という側面を忘れがちだと感じます。ですが、SINIC理論が指向する円環的な成長をするためには、持続性=時間の長さという量的なサスティナビリティだけでなく、質的なサスティナビリティ、例えば人々の心のサスティナビリティも重要な要素だと考えます。つまり、次につなげていくことにおいて何が重要であるかを深く考察している理論だと思います。
それに関連して、入り口としてはレス・バッド(Less Bad)が重要ですが、今後はますますモア・グッド(More Good)も大切な要素になります(※4)。それぞれが重要であり、問題解決だけに焦点を当てるのではなく、よりよい未来を創り出していく。両方をバランスよく考えることが今後重要になると感じました。
中間:JTが目指すのは、まさにモア・グッドの経営に入っていますね。
大瀧:そうですね。ですから企業の役割について考えると、サスティナビリティの議論と同様に、後輩や未来の仲間たちに何を残すかが重要だと思っています。経営において、負わないことによるリスク、つまり「不作為の罪」だけは残すな、と私はJTの諸先輩から何度となく聞いてきました。やはり「やっておいてよかった」ということが企業を救うことは往々にしてありますし。今の人たちができることをし、次世代に紡いでいくことが重要だと感じています。
中間:次世代に紡いでいくということを考えると、『グッド・アンセスター わたしたちは「よき祖先」になれるか』(ローマン・クルツナリック著)という本を思い起こします。
大瀧:福岡伸一先生の考え方にも通じるところがありますね。先生がご指摘されているロゴス過剰社会というのはまさに言い得ていると思います。合理・効率追求の社会を振り返り、ピュシスの重要性に気づく必要があるのだと感じました。そこに回帰することも、次に来る「自律社会」へとつないでいく重要な要素なのかもしれません。
中間:そのためにも「自律社会」へと移行するための準備は重要であり、エクセレントカンパニーならば、その余力も充分に持っていると思います。
大瀧:そうですね。やはりインサイド・アウトの限界に気づいている人も増えていると感じます。慣れ親しんだことや既知の情報をもとに未来の論点仮説を演繹的に考えるのは素晴らしいですが、その限界もまた、明らかになりつつある。そのような人々にとって、アウトサイド・インの視点を持つSINIC理論は共感できるものなのかもしれません。
中間:そうですね。演繹的か帰納的は、言い方を変えるとフォーキャストかバックキャストかという話になりますが、SINIC理論はバックキャストと解釈する方も少なくありません。
大瀧:SINIC理論は演繹と帰納の二択ではなくスパイラルアップ、いわば弁証法ですね。帰納法については、帰納の素材のバリエーションを増やしたり工夫をするのがアプローチのひとつとしてあると思います。演繹に関しては、自明と思えるものやルールを疑う、違和感に気がついて対応する。こうした資質はSINIC理論によって養えるように思います。
中間:問いが生まれますね。
大瀧:そうですね。その結果として、相容れない矛盾が何か新しいものを生む可能性があります。そこが弁証法につながるのではと思います。
中間:合成と分解を頭の中で弁証法のように考えると、なかなか難しいわけです。しかし、たとえ単細胞生物であっても合成と分解という相矛盾する行為を繰り返すことで生命を維持しているところが、生き物の素晴らしさではないかと思います。今私たちが向かおうとしている自然社会は、そうした生き物のあり方から人間が学び、そこから問いを見つけていくものになるのではないかと思いますが、いかがですか?
大瀧:ひとつのわかりやすい道として、未来創造や未来洞察、未来予測を事業戦略につなぐというアプローチがあると思います。私は組織と人をどうサスティナブルにするかに強い関心を向けていますが、できることは限られているので、少なくとも関わった人や組織くらいは幸せであってほしいと考えています。そのためにも、このSINIC理論の思想を少しずつ導入させる形で活用させていただいています。
そして、変化対応という言葉がありますが、その前段としての変化への準備と、変化への対応、そして変化を創出することの3つを兼ね備えることが、組織運営に必須だと思います。それについてもSINIC理論からヒントをいただいています。
※4 レス・バッド/モア・グッド:MITスローン経営大学院のピーター・センゲ(Leadership and Sustainability 上級講師)による、企業が悪いことを減らすアプローチの持続可能性対策を採用するのをやめ、ビジネスとそれを取り巻く世界の両方にとってよいことを増やすアプローチでの持続可能性対策を採用すべきであるという主張。
―― 未来の「よき先祖」になるための、適者生存を逆算する経営
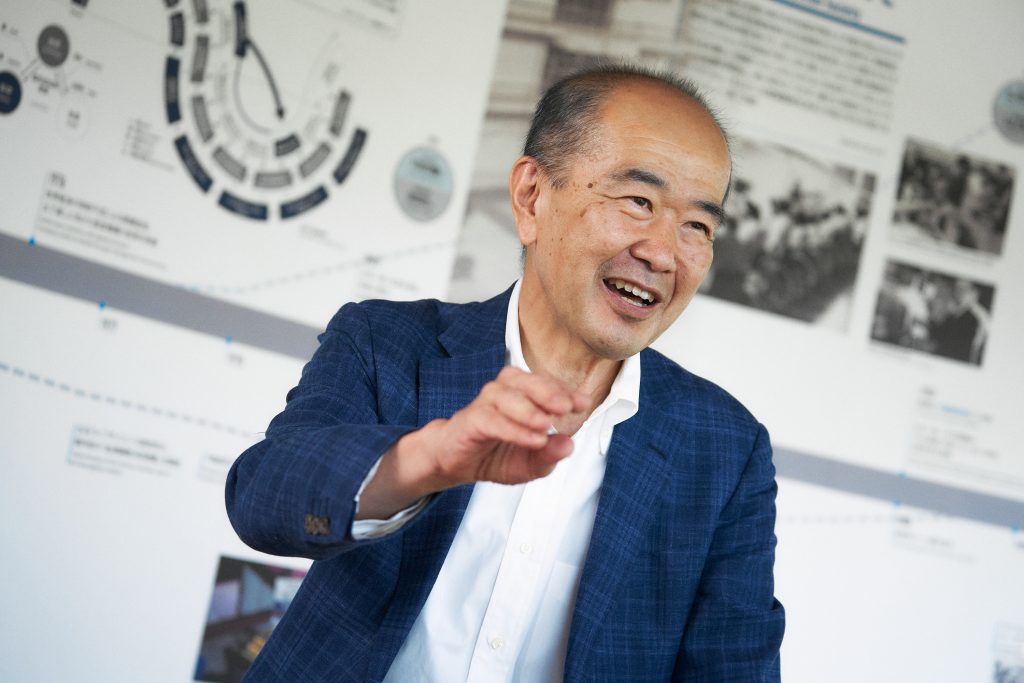
中間:SINIC理論を提唱した立石一真の頭の中には、「適者生存」という考えがあったようです。立石は独立後、自らのアイデアを形にしながら訪問販売や露店販売のようなことをしていました。その後、オムロンの前身である立石電機製作所を設立することとなりますが、その苦労の時代を経験したからこそ、社会のニーズに合った事業が生き残り、繁栄するということを身に染みてわかっています。
企業戦略的には常に未来を見据え、変化に対応する必要があるという話になりますが、私はそれだけでは足りないと考えています。生物の進化においては、適応しようとした種が必ずしも適応できて生き残ったわけではなく、適応できる種が偶然に残ったというだけにすぎません。
これをビジネスの世界に当てはめると、あらかじめ決め打ちせず、いくつかの近未来ソーシャルニーズの種をまいておき、そこから偶然に「適者」が出てくるという発想もあり得るのではないでしょうか。多様性という言葉が今注目されているのも、その兆しのひとつかもしれません。
大瀧:まさにD-LABが目指しているのは適者生存です。適者生存を達成するためには、突然変異の準備をいかにして現在の組織に組み込むかが肝要になると考えています。私がアメリカ留学からJTに帰ってきたとき、突然変異に対応できる組織をいつかつくりたいと考えていました。当時は30歳でしたね。今もD-LABの長期戦略目標には突然変異という言葉が組み込まれています。
中間:それこそグッド・アンセスター(よき先祖)への道ですね。
大瀧:そう考えています。正解かどうかはわかりませんが、たまたまうまくいく可能性もあると思います。いわゆる世の中における「競争優位」という言葉により過ぎないように心がけています。むしろ次なる飛躍に備える力を蓄えることこそが重要だと感じます。SINIC理論に通じるところがありますね。
――長期的な未来への航海に必要なものは、海図ではなく羅針盤

中間:SINIC理論はオムロンの経営における羅針盤と位置づけられ、未来への事業展開の指針として活用されています。
自動化や情報化社会という具体的な姿がわかりやすい社会ではビジネスこそしやすかったですが、これからの社会では最適化や自律性といった抽象的なコンセプトが必要になります。その際に解像度の高いマップ、つまり“海図(チャート)”を求めようとするのが一般的ですが、私たちは海図ではなく羅針盤を磨き続けたいと思っています。未来は長期的に見れば見るほど曖昧になっていきます。それらは見知らぬフロンティアにあるからです。ですから、解像度を上げるためには、自らのイマジネーションとクリエイティビティによって開拓するしかありません。そのために指針となるのが羅針盤です。
大瀧:私もまったく同感ですね。また私は、新しい地図は、新しい組み合わせのようなものだと思っています。シュンペーターの言葉によれば、イノベーションは新しい結びつきです。イノベーションが新しい結びつきにあるのだとすれば、不変なものは組み合わせ方の柔軟性だと感じています。新しい組み合わせを生み出すために、人々のクリエイティビティが駆動される必要性があり、そのために必要なものが羅針盤であるように思います。
中間:そうですね。現在の社会は、新しい結びつきにこそ関心を持ち、力を注ぐべき時期です。派手な新発明でなくても、新結合に大きな未来価値のチャンスがあると確信しています。
大瀧:その通りだと感じます。過去20年間に成長し存在感を示したスタートアップなどを見ると、多くは新しい需給のつなぎこみ、マッチングによるものです。例えば、Uberはタクシーを発明したわけではなく新しい組み合わせの発明でした。この点は学ぶべきことが多いです。
私たちが育った時代よりも、物質的な側面においてないものがなくなってきました。そのためアウトプットエコノミーも重要ですが、尾原和啓さんの著書にあるようなプロセスエコノミー(※5)の時代になってきました。
中間:アウトプットからプロセスへ、ということですね。アウトプットの尺度は経済力でのみ測られる傾向があります。しかし、プロセスは一義的ではなく、さまざまな尺度が存在します。そこが興味深いところです。ひとつのインデックスで終わるのではなく、さまざまな視点が求められる時代が始まるのではないかと思います。
大瀧:面白いですね。実際、私たちも同じ課題に直面しています。アウトプットエコノミーにおいては外からはすぐに目に見えるものや高解像度なものを求められますが、プロセスエコノミーにおいては、プロセスに関わるあらゆる人が価値を感じるかどうかだと思います。価値は受け手が判断するものなので、自由に判断していただくしかありません。その意味で、複雑系なのだと思います。ですから、あらゆる要素を見ておきたいです。
中間:言い方は悪いかもしれませんが、判断を任せるのであれば、少なくとも自分自身が非常に面白いものをつくるべきです。
大瀧:そうですね。自分自身が面白いと感じることを追求し、それを次のステップへと進める。
中間:自分自身が面白いと思えることが重要ですね。それを追求し、さまざまな視点を取り入れることで、適者生存の可能性が生まれるかもしれません。過渡期においては、自分自身が面白いと思えることに注目し、それを追求していくことが、よりよい未来への道かもしれません。
※5 「アウトプットエコノミー」「プロセスエコノミー」:「アウトプットエコノミー」は、アウトプットとして生み出されたプロダクトなどによって収益を上げる経済活動。一方の「プロセスエコノミー」は、アウトプットを生み出すプロセスにも価値を見出そうとする経済活動を指す。
―― SINIC理論をオープンにすることで、”We”の輪を広げる

中間:1970年に生まれたSINIC理論は、オムロンの経営の羅針盤として使われてきました。しかし50年以上のときを経て、社会課題の解決に向けて未来を見据える上では、この理論を社会の中でもっと広く活用し、みんなで活かしていく方が社会価値として大きくなると思いました。もはやオープンソースのように位置づけて、さまざまな視点を持ち寄り、解像度を高めて具体化につなげる活動が重要だと考えています。
大瀧:SINIC理論に限らず、新しい情報や思想は、受け手の視点や意識を考慮して、意味や価値を提供する必要があると思います。単に情報を発信するだけではなく、相手にとって意義のある形に変えていくということですね。
特にSINIC理論のような新しい視点や理論を広める際には、説明や伝え方が重要だと思います。相手が興味を持ち、意義を感じられるような情報提供を心がけることで、SINIC理論をふくめた新たな視点やアイデアが広まっていくと思います。
D-LABという組織としても、自己満足ではなく、他の人にとっても意義のあるものを提供することが重要だと何度も思い知りながら活動をしてきました。
中間:それは私も同じです。そうなると本当によりよい社会を実現できると感じます。今日はオムロンの創業者、立石一真が住んでいた場所である創業記念館を見ていただきましたが、大瀧さんはどのようなことを感じられましたか?
大瀧:やはり強く感じたのは、自律社会や自然社会への向き合い方です。効率や論理に重点を置くことも重要ですが、その逆の要素である感情や自然、情緒的なものを忘れてはいけないと感じましたね。また、オムロンさんの思想を広めるために、“We”の範囲をもっと広げたいという思いもあります。より多くの人々が”We”としてつながり、よりよい社会を実現することができればと思います。
中間:そうですね。私も同様に感じています。”We”を広げていくことは重要です。それによって、仲間の範囲が広がり、よりよい社会が実現する可能性があります。これからも、SINIC理論を広く伝える活動を通じて、”We”の共感の輪を広げていければと思います。境界を越え、さらに境界を溶かしながら、未来創造への共感の輪を広げていこうと考えています。
大瀧:同感です。境界をつくらずに溶かしていくことが重要ですね。

Writer:森 旭彦
大瀧 裕樹 JT(日本たばこ産業株式会社) D-LAB担当役員
1998年慶應義塾大学卒業(政治学)後、JT入社。2007年米国大学院卒業(MBA)。主にJTグループの経営戦略やたばこ事業の事業戦略の立案・実行を担当し、2013年にコーポレートR&D活動を開始し、現在のD-LABに至る。JTグループの長期的な未来創造をグローバルで仕掛けているところ。
中間 真一 株式会社ヒューマンルネッサンス研究所 エグゼクティブ・フェロー
慶応義塾大学工学部卒業、埼玉大学大学院(経済学)修了。株式会社ヒューマンルネッサンス研究所の創設メンバーとして参画し、「SINIC理論」を活かした未来社会研究に従事して現在に至る。著書に『SINIC理論 ~過去半世紀を言い当て、来たる半世紀を予測するオムロンの未来学~』(日本能率協会マネジメントセンター)、『スウェーデン―自律社会を生きる人びと―』(共著、早稲田大学出版部)、『北欧学のフロンティア』(共著、ミネルヴァ書房)など。

